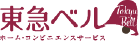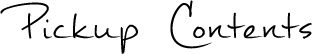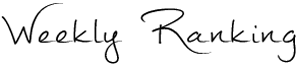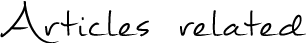女優・タレント 生稲晃子さんインタビュ
HUMAN
2017.08.04

生稲晃子さん
1986年におニャン子クラブに加入し、今年で芸能生活31年。移り変わりが激しい芸能界で、常にお茶の間の人気者として活躍してきた生稲さん。その笑顔とは裏腹に、2011年に乳がんが発覚以降、4年8カ月の闘病生活を余儀なくされることに。壮絶な経験から感じた体のことや家族のこと、仕事の話をうかがいました。
“おニャン子”は、学業優先通信簿も提出していました
――おニャン子クラブ時代を振り返り、
印象に残っていることはありますか?
私は、おニャン子に入ってから卒業するまで1年2か月なんですね。今振り返ってみると、たった1年間ですがすごくいろんなことを詰め込まれたような気がします。おニャン子でいる間は、学業優先。「掃除まできちっとしてから、フジテレビに来なさい。それで夕方の17時に間に合わないなら、(『夕やけニャンニャン』に出られなくても)それは構いません」と言われていました。通信簿をフジテレビに提出して、それもコピーされるんですよ。だから、成績が下がったとか出席日数もわかってしまうので、きちっとみんな守ってやっていたと思います(笑)。
――自分がこの仕事に向いてるかどうか
“おニャン子”卒業後に考える時間はあったのでしょうか
おニャン子に入ったときは、そのまま芸能界で進んでいこうとは全く考えてなくて。スタッフからも「生稲は最初に辞めるだろう」と言われていたんです(笑)。「お前は良い大学を出て、就職をして、良いお嫁さんになっていくのが一番合う」って。
最後の受験が終わって、その次の日から番組に戻ったんです。そのとき工藤静香ちゃんに「グループ作るらしいよ、『うしろ髪ひかれ隊』っていう変な名前だよ」という話をされました。だから自分で〝頑張ろう〟〝この先こうやって芸能界で生きていこう〟と思うことなく、『うしろ髪ひかれ隊』というレールに乗っけてもらったという感じです。
認知行動療法の免許取得40歳を過ぎてからの挑戦
――芸能生活の途中、
認知行動療法の免許を取得しています。
病気や怪我は治る可能性があるけれど、心の病は、私はなかなか治らないものだという頑な考え方があったんです。認知行動療法って日本ではほとんど聞かないけれど、欧米では鬱になった方の再発率がとても低い治療法と教えてもらったんです。最初は、頭にハテナマークでしたが、18歳から仕事を始めて資格というものもまったく持っていなかったので、学校に入って「理解したい」という想いから勉強を決意。すでに40歳を過ぎていたので、この歳からの勉強はなかなか頭に入らなくて大変でした(笑)。

カウンセリングの勉強というのは、自己カウンセリングから始まりますが、ぴったりと当たりまして。私の場合、自己否定型っていうのがいつも出るんですけど(笑)。乳がんという病気をしてから、随分前向きにもなれたんですが、ドラマで監督さんのオッケーが出てるのに、何十回もオッケーが出たセリフを言い直したりして〝違かったかな〟と思うタイプだったんです。
――「病気をして前向きになった」と言えるまで、
壮絶な体験もあったかと思います。
公表をしたのは、乳がん発覚から4年8カ月後でした。
ネガティブだった私が、自分自身の闘病生活をお話しすることで、元気や勇気を持てたという方が一人でも二人でもいてくださったら、自分が病気になったことも無駄ではなかったかもしれない。それは、後から考えれば認知行動療法を勉強していたからそんな風に考えられたのかもしれません。認知行動療法は簡単に言ってしまうと、マイナスの思考をプラスの思考に変えることによって行動も変わってくるよという療法なんですね。
“普通に”がんばれたのは家族の存在があったから
――乳がんという現実を突きつけられたときは、
どのような心境でしたか。
月並みな言い方ですけど、本当にショック、それしかなかったですね。最初に見つかったときは、自分のことしか考えられなかったです。2度の再発は、真っ先に子どものことを考えましたね。やっぱり“再発”“転移”っていう言葉は怖かった。素人ですから、その言葉を聞いたら〝もう終わりかもしれない〟というのがあったので。特に2度目の再発では、最悪の事態を考えました。ただ、当時まだ8歳の子どもを置いて逝くわけにはいかない。私自身、31歳の時に母を亡くしています。十分大人でしたが、それでもまだまだ聞くことっていっぱいあったなと、悲しかったんです。だからまだ子どもに、言わなきゃいけないことは母親として、いっぱいあると思ったら、生きなきゃいけないと思いましたし、一番苦しみました。
――講演活動でも自身の体験を語られています
自分が数年間闘病するなかで、どんな風に思ったか、どういう生活を送ったかということをお話しています。女性が多いのですが、男性で「自分の妻が病気になったとき、こうやって接していけばいいんだってことがわかりました」と言ってくださる方もいます。
――気を遣われるのは、嫌になりますか?
ただ患者になると勝手なもので、優しい言葉をかけてもらいたいと思う瞬間もあります(笑)。
自分の心の状況と一緒に、考え方も色々変わっていく。その繰り返しです。でもやっぱり、買い物も行くし、洗濯もするし、ご飯も作るし“やらなきゃだめじゃん私が!”っていう頑張りを作ってくれたのは、家族が普通に接していてくれたから。それは、私にとっては良かったのかなと思います。

がん患者でもやりがいを持って社会を生きて行ける世の中に
――2016年の『働き方改革実現会議』では、
有識者として名を連ねています。
そこではどのようなことを発信されましたか。
『トライアングルサポート体制』というのを提案させていただき、実行計画案にも盛り込んでいただきました。自分ががん治療してるということを周りに言えない、でも治療しながら仕事をして苦しい思いをしている方がたくさんいるということを自分ががんになってわかったんです。同情はしなくてもいい。でも理解と共感は、周りがしなくてはいけないと思うんですね。社会全体がそういう状況を把握して、サポートしていく体制が必要。そのためには、病気のことを理解している病院、その方の人となりを理解している会社、病院と会社の連携が必要になってくると思ったんです。
――実現すれば、スムーズな治療、
仕事復帰が見込めそうですね。
まずは患者さんが主治医の先生に、いまの自分の勤務時間、通勤時間、勤務状況などを伝えます。主治医がそれを踏まえ、今できること、できないこと、今この方の治療はこんな感じですといった意見書のようなものを患者さんに戻し、それを会社に提出する。これを会社が当人と産業医なども含め話し合いをもって、できる仕事をしていく。身体の状態は悪くなったり良くなったり日々変わっていくので、定期的に見直しをしていく、このようなシステムが理想だと思うのです。
会社にとって、社員のみなさんは財産。患者である労働者のみなさんも、いままでせっかく頑張ってきたキャリアをそこで失うのは、自分のため、家族のためにしてはいけないことだと思います。
――様々なことを経験されてきました。
今、毎日をどのように過ごすことが大切だと考えますか。
人間って長く生きてくると、いろんな欲が出てくると思います。でもやっぱり基本は、今自分が持っているものに感謝して、穏やかに生きていく、それが一番幸せな生き方なんだということを病気になって学びました。普通ということが、いかに大切で、一番尊い生き方なんだなと感じます。子どものことで一生懸命になったり、夫婦仲が悪くなったり、病気になったり、いろんなことが詰まっている30代から50代。だからこそ自分に〝普通に生きよう〟と言葉を投げかけてあげることが、必要ではないかと思います。
[聞き手から]
仕事や家事に追われていると「普通に過ごせる」幸せはなかなか実感できません。生稲さんが経験された再発を含む4年8か月という闘病生活は、日々の中にある「普通」というありがたみをリアルに感じることができるようになった契機のようです。手記を拝見すると想像を絶する内容が多々ありますが、それらも笑顔で前向きにお答えしてくれる姿勢に頭が下がる思いでした。
女優・タレント
生稲晃子さん
1968年4月28日生まれ。東京都出身。1986年に『おニャン子クラブ』のメンバーに抜擢され、一躍国民的人気者に。〝おニャン子〟卒業以降は、女優、タレントとして、テレビや舞台等で活躍。女優業の傍ら、「鉄板焼 佐吉」(東京都港区)の経営も営む。著書に自身の乳がん体験を記した『右胸にありがとう そして さようなら』(¥1,300+税、光文社)。


ネギの栄養の主な効能5つ!ネギで風邪予防 体の内側から健康に
BEAUTY & HEALTHY


BEAUTY & HEALTHY




BEAUTY & HEALTHY